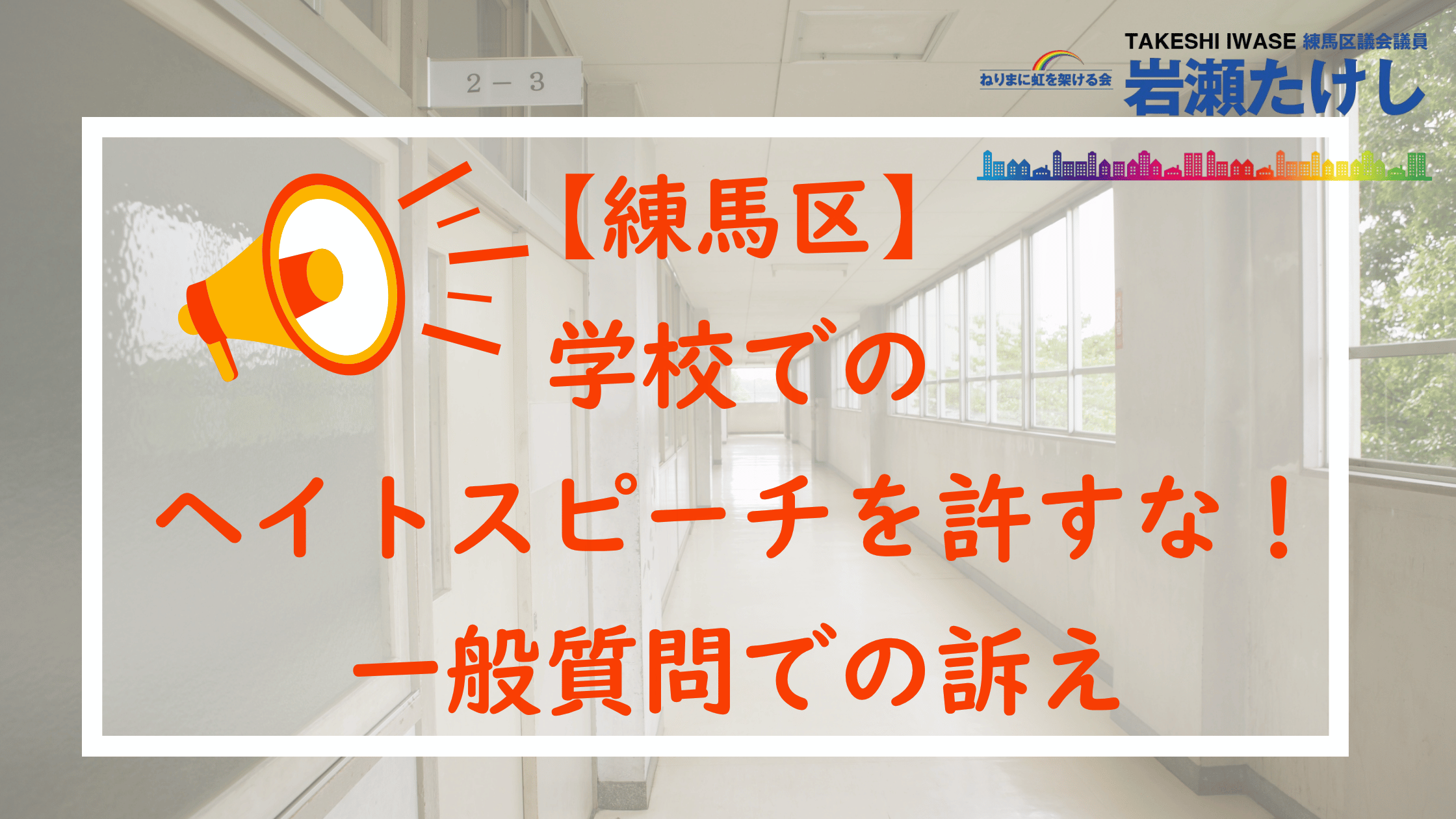9月の一般質問では、練馬区内でも広がりを見せる排外主義やヘイトスピーチについて、特に学校での対応について訴えました。
戦争への入口は銃声ではなく排外主義から始まる。それが歴史の教訓です。
本年8月、練馬区の人口は初めて75万人に到達。この1年で日本人は約1,300人増、外国人は約3,350人増。区民に占める外国人比率は約3.8%に達し、地域における多文化共生の重要性はかつてなく高まっています。
はじめに
区は第3次ビジョンで「外国人に選ばれる国になれるかどうかは我が国の未来を左右する重要な課題」としたうえで、「基礎的自治体として受入れ環境を整え、開かれた地域づくりを進める」としています。しかし一方、地域でも外国人に対する排斥的な動きが急速に拡大しています。
東京都は、人権尊重条例(通称)に基づき、ヘイトスピーチに該当すると認めた表現活動の概要を公表し、申出窓口も設けています。「不法滞在者は日本から出ていけ」といった表現も典型例として示され、許されないものと明確に位置づけられています。
(出典)
・ヘイトスピーチの具体的な事例:東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第14条の規定により設置する審査会での事例
1. 排外主義、学校に広めない取組を!
ヘイトスピーチは言葉のナイフ、人を傷つけ、死にすら追いやるもの。特に子ども達に与える影響は深刻です。外国にルーツを持つ子どもたち、その多くは地域に溶け込み、共に学校生活を送っています。「日本人ファースト」といった言葉も、誰かを優遇し、誰かを後回しにしてもよいという「人間の順位付け」のメッセージも含みます。発言者の意図ではないかもしれませんが、こうした言葉が子ども達に広がれば、修復不能な心の傷を生みだしかねません。
文科省もヘイトスピーチ解消は重要な課題として、学校での適切な対応を求めています。しかし現場からは、どんな言葉が差別かわからない、またどう対峙していいか戸惑っているとの声もあがっています。そこで学習指導案や研修で「何がヘイトスピーチにあたるか」を具体的に扱うとともに、児童生徒・保護者に対して「排除の言葉は絶対に許されない」旨を周知すべきです。また、子どもがなぜいけないのかを学び、行動につなげていくために、学活の時間などで、具体事例のロールプレイなどを実施すべきです。これは理念の話ではなく、生存権や学習権に関わる重大な問題です。区の回答を求めます。
【練馬区の回答】
ヘイトスピーチは決して許されるものではない。区では毎年、人権教育研修を実施し、ヘイトスピーチの実際の事例等も取り上げながら、教員の人権意識の向上を図っている。
各学校においては、社会科や道徳等の授業で差別やヘイトスピーチに関する人権教育を行っている。人種や民族などに対する具体的な差別の事例を紹介し、児童生徒同士で問題点を話し合い、互いに尊重しあおうとする意欲や態度を育んでいる。
【岩瀬の意見】
答弁にある取組は評価します。ただ、海外事例の紹介に偏らず、国内・都内の実例(都の公表事案等)を教材に反映し、「具体的に何が差別か」を教職員・児童生徒の共通理解にすべきです。また、校内研修の演習化なども必要です。
2.ヘイトスピーチ通報窓口の周知を!
また、区としてヘイトスピーチに正面から対峙するためにも、区のウェブサイトで都の通報窓口を紹介するとともに、選挙など差別的言動が増えやすい時期には専門窓口や多言語対応を拡充すべきです。さらに都の公表事例を周知し「この種の言動は許容されない」と明確に発信すべきです。区の回答を求めます。
【練馬区の回答】
ヘイトスピーチへの対応は都条例に基づき行っており、区のホームページに申出先や公表事例を掲載した都のホームページへのリンクを掲載している。選挙期間中については、人権男女共同参画課、選挙管理委員会事務局、外国語相談窓口などが連携して対応することにしている。
【岩瀬の意見】
区は様々な対応を取っているとしていますが、多くの区民がヘイトスピーチについて知る機会を持つようにもっと周知していく必要があります。
3.練馬区も「ヘイトスピーチは許さない」という姿勢を!
区は今年度、15年ぶりに「外国人施策の在り方方針」を見直す予定です。世田谷区、目黒区などではこれらの方針の中でヘイトスピーチの根絶を正面から打ち出しています。練馬区も新たな方針のなかで「ヘイトスピーチを許さない」という明確な姿勢とともに、区独自のヘイトスピーチ禁止条例の制定を見据えた方向性も示すべきです。区の見解を求めます。
【練馬区の回答】
2025年3月、第6次男女共同参画計画を策定、そのなかで、ヘイトスピーチ等の解消に向けた啓発なども実施している。区条例を制定する考えはないが、ヘイトスピーチ等の様々な人権問題に関して、引き続き啓発等の取組を進める。
今後に向けて
練馬区は15年振りに外国人施策を見直す計画を進めています。今こそ、練馬区としても正面からヘイトスピーチに向き合うこと、排除ではなく共生を選ぶ練馬となるよう強く訴えていきます。
過去の訴えはこちらからご覧ください。
(出典)
・都の制度:東京都「申出について」「不当な差別的言動の公表」。東京都総務局
・定義と典型例:法務省
・学校現場の位置づけ:文科省「人権教育・年次報告」等。文部科学省
・他区の方針例:世田谷区第二次多文化共生プラン、目黒区の人権啓発。世田谷区公式サイト