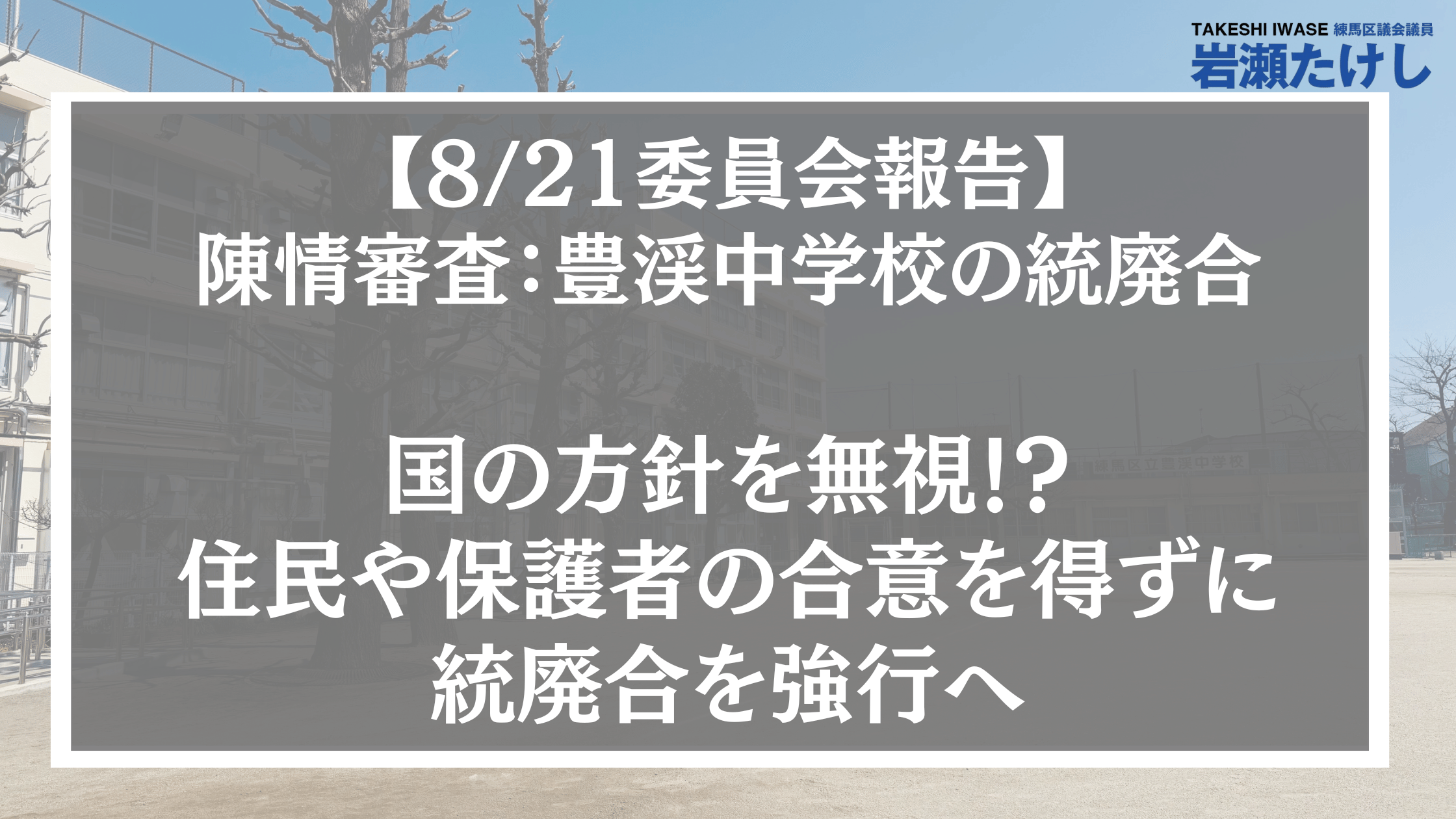8月21日(木)の文教児童青少年委員会で、豊渓中学校の統廃合の中止を求める3本の陳情(第99号・第104号・第105号)が質疑されました。陳情には合計で約1,900名の地域の皆さんに加え、町会長・避難拠点会長・コミュニティスクール(CS)会長など、地域を代表する当事者が名を連ね、「合意形成のないまま進めないでほしい」と訴えています。
それにもかかわらず、委員会で区は統廃合に住民からの「一定の理解は得られた」として、計画を「素案」から「案」へ格上げし、前に進める姿勢を崩しませんでした。私は委員会で、住民の理解や協力が得られていない中で統廃合を進めるのは国の方針に反すると訴え、改めて計画の撤回を求めました。
■ 練馬区は国の方針を無視
国の学校統廃合に関する手引きでは、学校の適正規模・適正配置(統廃合)の検討について、「行政が一方的に進める性格のものではない」と明言し、保護者や地域住民の「十分な理解と協力」を得て丁寧に議論を尽くすことを求めています。
さらに、現在進む手引きの見直しの議論でも、統廃合については「地域・保護者・子ども等の関係者の参画を得ながら」検討し、対話と議論のプロセスを大切にすること、地域が“自分事”として考えられる仕組みづくりの必要性が繰り返し示されています。
★参考資料
- 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について(通知)(平成27年1月)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1354768.htm - 「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議(第5回)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/195/giji_list/mext_00005.html-
参考資料1:これまでの議論の整理(PDF)
https://www.mext.go.jp/content/20250807-mtx_syoto02-000043703_4.pdf
-
■説明会やパブコメは「合意形成」ではない
区は住民の理解を得るために「説明会で丁寧に説明した」「パブリックコメントも実施した」と述べます。しかし、住民説明会は情報提供と意見聴取(=広聴)の場であり、合意形成の場ではありません。
パブリックコメントも、提出意見を“十分に考慮”し、結果を公示する法定手続(行政手続法第42条・第43条)でしかなく合意形成ではありません。区がパブコメの実施で統廃合への一定の理解を得られたというのであれば、そこで寄せられた約9割の意見は反対だった中で、その意見を尊重すべきです。
だからこそ国は、現在進行中の手引きの見直しの中で、統廃合の決定には「参画のプロセス」そのものを設計し、実行せよと明記しています。説明会やパブコメの実施=合意形成ではありません。
■ 学校運営の核、コミュニティ・スクールを軽視
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度/CS)は、地域・保護者が学校運営に制度的に関与する公式の仕組みで、校長が作成する学校運営の「基本方針」を承認し、運営への意見申出ができます(地教行法に基づく制度)。
練馬区での初のCSが豊渓中で始まったばかり。それにもかかわらず、区は統廃合についてCSの正式な同意・審議を取ろうとしないのが現状です。法令が「CSの同意」を厳格に義務づけていないとしても、“制度的参画の窓口”を素通りした事実は重いものです。板橋区など多くの自治体では、統廃合の際にCSの同意・議論を重視しています。国の掲げる参画重視の趣旨に真っ向から逆行しています。
■ 住民の理解や合意は、いまだ成立せず
陳情人は約1,900名。その中には町会長・避難拠点会長・CS会長など、地域の要となる当事者も参加しています。パブコメでも約9割の住民が反対の意思を示しています。区が「一定の理解は得た」というならなぜこれほどの方が反対の意見を表明したのでしょうか?
■ 計画案の撤回を!
学校の統廃合は、子どもたちの学びだけでなく、地域コミュニティや防災の基盤にも直結します。だからこそ、「ともに決める」ための設計が必要です。
説明は合意ではありません。
8月28日には提出された陳情について、文教児童青少年委員会としての意思を決める審査が行われます。
住民の理解と協力が得られていないまま統廃合を進めることは、国の方針にも反します。
地域・保護者・学校が同じテーブルに着き、手続を整え、納得して進むために、いったん立ち止まり、合意形成に向けた努力を行うべきです。ぜひご意見などお寄せください。
過去の訴えはこちらをご覧ください。
★参考資料
-
- 陳情第99号:保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めることについて
- 陳情第104号:教育学的根拠が不十分な学校統廃合対象校の区独自選定基準の見直しについて
- 陳情第105号:豊渓中学校を対象とした学校統廃合計画を見直し、地域の声の反映を求めることについて
https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/seigan/hutaku/R7hutaku.html - 区立学校適正配置第二次実施計画(素案)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/tekisei/keikakuhaiti/tekihai_keikaku2soan.html - 豊渓中学校・光が丘第一中学校 保護者および地域説明会(資料PDF)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/tekisei/keikakuhaiti/tekihai_keikaku2soan.files/siryo_ho-kei2.pdf
★当日の委員会資料
- 【資料1-1】陳情第99号・陳情第104号・陳情第105号 保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めること 等について
- 【資料1-2】陳情第99号・陳情第104号・陳情第105号 保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めること 等について
- 【資料1-3】陳情第99号・陳情第104号・陳情第105号 保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めること 等について
- 【資料3】区立学校適正配置第二次実施計画(素案)に寄せられた意見と区の考え方について
- 【資料4-1】区立学校適正配置第二次実施計画(案)について
- 【資料4-2】区立学校適正配置第二次実施計画(案)について