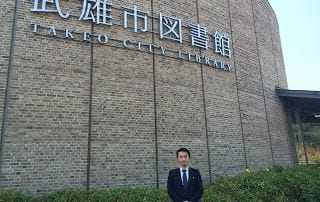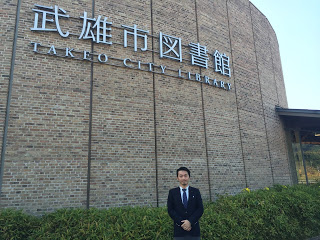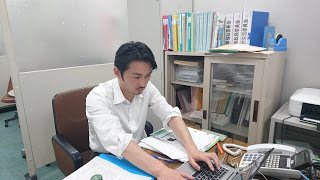一般質問のご報告② 外国籍住民の人権保障について
先日行った一般質問、二つ目のテーマとして、外国籍住民の権利保障と多文化共生についてとりあげました。こちらのテーマについても、性的マイノリティと同様、議会で取り上げられる機会は少なく、特に地域に住む外国籍住民の権利保障について議論するのは、昨年の私の質問がほぼ初めてでした。今回は先日制定された通称ヘイトスピーチ対策法を受けての区の政策、そして、練馬区の多文化共生事業への取組について質問しました。
全体的には、私の提案について、特にヘイトスピーチに対する区の対応について前向きな回答を引き出せたと感じています。
他方、多文化共生については不満の残るものでした。私は、多文化共生を進めるためには、長期的な視点を持ち、外国人外国籍の方のニーズを的確に把握するとともに、外国人外国籍の方が一部分野だけでなく、区政や地域の町づくり全般に積極的に参画することが必要だと考えています。しかし区は、多文化共生を「2020年のオリンピック・パラリンピックの開催にあたって大切な課題」という一面的な見方でとらえており、回答も満足できるものではありませんでした。以下は私が一部まとめたものです。(正式な議事録ではありませんので、間違いがある可能性もあることをご了承ください。)
<質問1>
国会では先日、通称「ヘイトスピーチ対策法」が成立しました。この方は、差別的言動は許されないことを宣言する」もので、いわゆるヘイトスピーチを規制する初めての法律として大きな意義を有するものです。そこで、ヘイトスピーチ対策法の成立を受け、練馬区としても相談体制拡充、教育、啓発のためにさらに積極的な対応をすべきです。区の考えをお聞かせください。
<回答>
今回の法律の成立を機に、差別的言動の解消に向けた効果的な区民への啓発や相談支援の有り方、職員研修など、人権尊重に係る事業の充実に努めてまいります。
<質問2>
この法は、保護の対象者を「本邦に適法に居住するもの」と規定しており、その結果、日本にルーツを持つアイヌ民族などの少数者や、難民申請者を含む在留資格を持たない外国人が保護の対象とされていないかのような印象を与えるおそれもあります。
しかし、練馬区が今後ヘイトスピーチに関わる施策を進めるにあたっては、付帯決議にも記載されているように、保護対象者を法律に規定されているような「本邦に適法に居住するもの」に限定すべきではないと考えます。区の見解をお聞かせください。
<回答>
国籍・民族等を理由として地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは、不当な差別的言動であり許されるものではないと認識しています。そのため、同法の立法主旨と附帯決議を踏まえ、対象となる方の範囲についても十分配慮して事業を実施してまいります。
<質問3>
ヘイトスピーチによる人権侵害をなくすためには、現に起こっているヘイトスピーチを禁止する、あるいは拡散させないための対策に乗り出すべきです。区の見解をお聞かせください。
<回答>
法律では、ヘイトスピーチなどの差別的な言動や行動について罰則規定が設けられていないため、区としての直接的な禁止対策は現時点では考えておりません。
法に定められた相談体制の整備、教育の充実、啓発活動の推進等の対策について、検討を進め不当な差別的言動の解消に努めてまいります。
<質問4>
練馬区では、かつて存在した国際交流課や文化国際課が担っていた多文化共生への取組は、地域振興課へ移管されました。しかし、地域振興課の中に多文化共生事業を専門に行う「係」はおろか、専任で担当する職員すらいません。区における多文化共生事業は縮小の一途をたどっていると言わざるを得ません。練馬区でも多文化共生施策を専管する「係」以上の組織を置き、併せて全庁的に取り組みを推進する体制を取るべきと考えます。区の見解をお聞かせください。
<回答>
事業が縮小の一途を辿っているとの指摘は当たりません。多文化共生事業については、係の事務分掌として明確に位置付け、取り組んでいます。
<質問5>
区民や区内の団体、外国人を構成員とする連絡会を設置することが掲げられていました。しかし、3年以上にわたって連絡会が設けられていません。早急な設置を行うべきであるとともに、設置に向けた具体的なスケジュールをお答えください。
<回答>
多文化共生は、オリンピック・パラリンピックの開催にあたって大切な課題です。連絡会の設立を含め、すでに検討を進めています。
中村哲医師の話を聞いて
昨日、「市民の声ねりま」主催で「中村哲医師講演会 アフガニスタンからのメッセージ、命を支え平和を紡ぐ」を開催しました。
中村先生は医師として、当初は医療支援を目的にアフガニスタンに赴任しましたが、そこに住む人々が抱える問題には医療だけでは不十分であると考え、30年以上にわたり、灌漑事業などに力を注いできました。
練馬文化センターの大ホール、1500名もの方にお越し頂けるか、心配していたのですが、皆さまのご尽力のおかげで、前売り券だけでほぼ完売するなど、たくさんの方にお越し頂くことができました。
私自身も区議になる前、国際協力に携わるものとして、隣国のパキスタンなどのアジア、アフリカ、中南米諸国で10年以上にわたり地域開発を行ってきました。その中で実感したのが、本当に大切なこと、というのは、海外の私たちが援助を施す、ということではなく、現地に暮らす人々自身が主体となって前に進むことの手助けをする、ということでした。
その中で、中村先生の活動というのは、現地の人々とともに生き、仕事を行い、ともに前に進むということを、地道に、ぶれずに実現されてきたもので、心から尊敬するとともに、お話を伺う事を楽しみにしていました。
今回の先生のお話、特に印象に残ったのは、「集団的自衛権」に関するものでした。「武器を持つこと、見せびらかせることで解決できることは少ない。むしろ、武器をもつことが問題を産むことの方が多い」ということ、そして、先生自身の活動での思いとして「私は誰の心にも良心があると信じている。そして、その一人ひとりの良心に働きかけて活動をしている。」という言葉でした。静かで、朴訥にも感じられる話し方の中に感じられる先生の強さに圧倒されるとともに、私自身も勇気をいただける、そんな素晴らしい経験でした。(写真は前回の講演会の際のものです。)
文教児童青少年委員会のご報告① 図書館での指定管理の導入について
先日、所属する常任委員会の文教児童青少年委員会が行われました。
主な議案(議会で賛成、反対の意思を決定するもの)は大きく3件、1つが関町にある図書館の運営に指定管理業者を導入するもの、残り2つは、練馬区の5小学校の学童クラブをねりっこクラブという新しい制度に変更するものでした。
まずは、関町図書館での指定管理業者(民間企業等)の導入について、ご報告します。
練馬区には合計で12の図書館がありますが、平成21年から指定管理業者の導入が始まり、これまでに8館での導入が進みました。区の説明では、指定管理業者の導入の大きな目的は、「経費の削減」と「サービスの向上」としています。
図書館の運営を民間企業等が担う、というと、「コストも下がるのだし、別に問題ないのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。しかし、大きな問題の一つは、指定管理業者を導入することでなぜコストが下がるのか、ということです。
指定管理に委託した際に削られる費用、その大半は人件費です。現在、全国の図書館で指定管理の導入が進んでいますが、そこで働く方々の労働条件は、非常に厳しく、他の自治体では、司書資格を持っていても時給は最低賃金、ダブルワークをせざるを得ないという方もいます。
そんな問題意識から、最初に練馬区の指定管理の図書館の現状を確認したところ、ある館では53名の職員の内で、非常勤の方が45名に達しているとのことでした。これでは、働く方々の労働条件を見ても、継続性や安定性、また事業の安定性を確保できているとはいえません。加えて、指定管理の図書館で働く方々の賃金、そして3年以上継続して働いている方の比率を問うと、「指定管理業者に委ねているので区として数値を把握していない」とのことでした。
練馬区は、指定管理業者を導入したことで、サービスが向上した、としていますが、その大きな理由は開館時間が拡大したこと、利用者アンケートの満足度が8割を超えている、というものでした。しかし、開館時間の拡大は、指定管理でなければできない訳ではありません。利用者アンケートも、指定管理の満足度がそうでない館に比べて高い、という事実はなく、方法も、窓口で渡すだけで性別、年齢、属性なども不明、調査数も登録者数21万人に対して、わずか2%、さらに調査項目もあいまいで、統計として用いることができるのかも不明です。
そもそも、サービスが向上すれば、そこで働く職員の労働条件は悪くてもいい、ということはありません。
こうした状況の中で、結論ありきで指定管理の導入に前のめりになるのではなく、まずは現在の館の状況について、労働条件がどのようになっているのかなどを精査すべきだと訴えました。
(写真は昨年の視察で訪問した佐賀県の武雄図書館です。)
一般質問の報告① 性的マイノリティの人権保障について
先日の一般質問、主題は「マイノリティの権利保障」でした。
質問では1. 性的マイノリティの権利保障について、2. 外国籍住民の権利保障および多文化共生社会の実現について、3. 待機児童対策について、4. まちづくり(大江戸線延伸)を取り上げました。
本日は、その中で、性的マイノリティの権利保障について抜粋をご報告します。待機児童問題については、区長のひどい答弁もありましたが、性的マイノリティの問題については、具体性の乏しい部分もあるにせよ、全体的にはある程度、前向きな答弁だったと感じています。
特に、教職員向けの性的マイノリティに関する研修プログラムの実施については、学校として組織的に取り組むことを言っており、前進だと思います。また、情報コーナーの設置や交流会についても、前向きな回答でした。
(正式な議事録ではないので一部誤りがある可能性もあることをご了承ください。)
<質問1>
各学校には、(カミングアウトが前提とされる)性的マイノリティの児童生徒が在籍していることが明らかな場合にのみ、対応を求めるのではなく、こうした児童生徒が存在することを前提として対応を求めるべきだと考えますが区の認識をお聞かせください。
<区の答弁>
児童生徒が様々な人権課題について学び、人権尊重の精神を生活の中で生かしていくことができるよう、教育活動全体を通して組織的・計画的に人権教育を推進しており、性的マイノリティについても、人権教育の一環として行っています。
<質問2>
学校では「違い」を「個性」と捉え、認め合うべき事を授業等の中で積極的に発信することが必要です。また、図書室や保健室等に、性的マイノリティに関する書籍を置く、ポスターを貼るといったことを通じて、学校として当事者への理解を表明すべきです。この提案に対する区の認識を聞かせてください。
<区の答弁>
学校における啓発の取組やその方法につきましては、各校が自校の実情を踏まえ、児童生徒の発達段階に応じて工夫していきます。
<質問3>
練馬区として、文部科学省が教職員向けに対して発行した性的マイノリティの児童・生徒への配慮を示した手引きに従い、教員研修プログラムを早急に策定すべきだと考えますがプログラム策定に向けた区の考えを聞かせてください。
<答弁>
教育委員会として、この資料を踏まえて、教員研修の計画を立案し、副校長対象の研修会や希望する教員を対象とした人権教育研修会を実施していきます。研修を通して、性的マイノリティに関する理解啓発を促進するとともに、各校における研修の中心的役割を果たす人材を育成し、各校が人権教育担当者や生活指導担当者、養護教諭等を中心に組織的に取り組めるよう、指導してまいります。
<質問4>
相談窓口は、性的マイノリティの方を対象とすることを改めて周知するとともに相談員を対象とした基礎研修の実施、そして、他自治体や支援団体等の相談事例を収集し、相談対応向上のための情報共有を図るべきです。区の所見をお聞かせください。
<答弁>
男女共同参画センターを含めた相談窓口を充実するため、適切な支援に繋ぐ専門機関等との連携や職員の専門研修の受講、他自治体や支援団体等の相談事例の収集など準備を進めています。
<質問5>
小・中学生を対象に、学校でこの相談窓口を含め、親や学校を通じずに相談できる場を紹介すべきです。この提案について区の所見を聞かせてください。
<答弁>
小中学校では、性的マイノリティを含めたさまざまな相談に関して、リーフレットや案内カードの配布、校内でのポスター掲示などを用いて、区の教育相談室、東京都教育センター、文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」等を紹介しています。今後も児童生徒への相談窓口の周知を図ってまいります。
<質問6>
練馬区は区立施設を活用し、情報コーナーを設置し、役立つ情報を取りまとめ発信すべきです。情報コーナーでは、性的マイノリティ関連図書、資料等をそろえるとともに、区や支援団体の取組を紹介し、性的マイノリティ関連のイベントを開催すべきです。同時に、横浜市が実施しているような当事者や支援者の交流の機会を設けるべきです。
<答弁>
区立図書館や男女共同参画センターの図書・資料室では、性的マイノリティに関連する書籍の購入、貸出しを行っています。引き続き、人権パネル展や男女共同参画センターを活用した情報コーナーの設置など、さまざまな事業や機会を捉えて効果的な情報発信方法を工夫してまいります。当事者や支援者が交流する機会として、男女共同参画センターにおいてワークショップを開催いたします。今年度の人権セミナーにおいて、当事者による講演会なども予定しております。
(写真は先日参加した東京レインボープライドの様子です。)
一年を終えて
議員になって初めての議会が、ちょうど一年前の6月(第二回定例会)でした。この間、議会に対して抱いていた理想と現実が大きく異なるということに何度も気づかされています。象徴的なのが、先日の一般質問での野党と区とのやり取りでした。
全ての議員は、賛成の立場であれ、反対の立場であれ、「練馬区をよくしたい」という思いは変わらない、そして、一般質問で各会派が発言し質問することも、そういった思いに基づくものと信じています。
だからこそ、議員は地域の中でたくさんの声を聞き、それを政策として形にするために一般質問に臨む。そして行政は各会派の質問や提案に対して、真摯な態度で臨み、協力できること、改善できることをしっかりと受け止めていく、そういった建設的な議会の姿を想像していました。
しかし、実際には、特に野党に対する区の答弁には、真摯さ、誠実さが欠けている、そう思わざるを得ないことが何度もあります。例えば、先日も野党の質問に対して、区の答えには「言うまでもなく」、「ご指摘は全くあたりません」、「ご指摘を待つまでもなく」、「よく確認いただきたい」といった表現が並び、特に「言われるまでもなく」という表現は、わずか20分の答弁の中で10回近く繰り返されていました。
こうした姿勢、決して建設的ではありません。
こうした議会の姿に愕然とするとともに、しかし、そこで諦めるのではなく、そのなかで、何が出来るか模索し続けてきました。
いま改めて、「もっと頑張らねば!」と思います。第二回定例会は6月17日(金)まで続きます。ぜひお気軽に傍聴へいらしてください。
二回目の一般質問
本日、一般質問を終えました。
一般質問は練馬区では、全ての議員が年に1度、議会の場で、区長に対してどのようなことでも報告や説明を求めることができる貴重な機会です。
準備にあたっては、たくさんの方から区政への思いや改革へのご提言を頂くことができ、そして、直前にはお腹の風邪による絶食というアクシデントもありましたが、家族や、皆さまのご支援のおかげでなんとか完成させることができました。
そして当日。
議場に立つと、目の前には議長以外の全議員が座っていて、毎回とても緊張するのですが、平日の昼間にもかかわらず、30名を超える方が傍聴席へと応援に来てくださっていて、一人ひとりのお顔をみただけで、とても勇気づけられました。
今回の一般質問、具体的な内容については明日以降にご報告しますが、とても残念だったのが、私の発言に対する区長の答弁(意見)でした。
昨年行った初めての一般質問では、区長に答弁を求めたのにもかかわらず、区長は一度も答えなかった、ということがあり、今回は答弁するのか、また、その場合何を発言するのか、ということに注目していました。以下が、待機児童対策の質問に対する区長の答弁(抜粋)です。(正式な議事録ではないので、誤りがある可能性もあります。)
<待機児童対策について>
「岩瀬議員にお答えするのは初めてですが、大変細部にわたるご質問を頂き、感心しながら聞かせていただきました。しかし、残念ながら、私はご質問に違和感を覚えざるを得ないのであります。(中略)…本来、待機児童をはじめとする子育ての支援は、自治体の保育行政だけでなく、育児休業などの労働政策や児童手当などの所得政策などを含めた総合的な政策として、国が取り組むべきものなのです。なぜ、国を批判するのではなく、微力ながらこれだけ頑張っている練馬区を責められるのか、全く理解ができないのであります。本末転倒ではないかと思います。
私はこれまで長い間行政と政治の現場にいて、色々な方々を見てきました。はじめは社会正義から出発したはずの活動が、いつの間にか行政への反対それ自体を自己目的とするようになる。そういう場合がままあります。極端な場合には、反対するという結論がまずあって、そのために無理やりあらさがしや揚げ足取りをされる方もいます。若い岩瀬議員は決してそうではないと思いますが、ぜひ内容のある建設的な対案を頂くようお願いいたします。」
(ここまで)
区長の答弁、練馬区は今年4月までに待機児童をゼロにすると約束したにも関わらず、166名発生したという事実に対して、区の責任を全く認めていません。そもそも、保育所の設置者は、地方公共団体であり、また、国と地方公共団体の関係性は上下ではなく並列であるはずです。また、これは個人的な感想ですが、区長が公の場でことさら「若い議員」として扱うこと、反対することを目的に活動しているかのような回答をすること、誠実な回答とは思えません。区長のこの答弁が現在の区政を象徴していると感じます。
おなかの風邪
一般質問の準備で全く余裕がない日々。先日、ようやくひと段落ついて、床についたら、夜中に大変な腹痛に…トイレに駆けこみました。しばらくして収まったと思ったものの、翌日も全く回復せず。
お腹を抑えながら、「これほど苦しかったのは、5年前、当時働いていた会社の近くで、先輩にランチに誘われて食べたエビフライにあたって以来だな。しかも、あの時、先輩はなぜかオムライスを頼み、私だけが悶えたんだった。生焼けのネズミを途上国で食べても大丈夫なのに、なぜ毎回日本でやられるんだ」とどうでもよいことに思いをめぐらせる。
夜には腹痛だけでなく熱も出てしまい、さすがにまずいと病院に行ったら、「おなかの風邪」と診断されました。注射ともにたくさんの薬をいただいて、そのまま議会に登庁。さらに、お医者さんからは「今日は絶食!」と言われてしまい、腹痛と空腹のダブルパンチ。
でも、薬が効いたのかようやく回復の方向に。月曜の一般質問までには間に合いそうです。
練馬区議会の開会
いよいよ議会が始まりました。
今回の議会(第二回定例会)6月1日から17日までと、短期間ですが、年に1度の「一般質問」を行うこととなり、私にとってはいつも以上に重要な議会となりました。私の一般質問は6月6日(月)の13時45分からとなります。
一般質問は、練馬区ではすべての議員が年に1度、練馬区に対してどのようなテーマでも訴えることができる貴重な機会です。議員が25分質問をし、それに対して区が20分答弁をする形式になります。
一般質問の準備にあたっては、現在の区に対する、たくさんの方の生の思いや訴えを伺うことができました。一人ひとりの思いや声がなるべく質問の中に息づくように全力を注いだつもりです。
一般質問の主題は、議員になる前から力を注いできた「マイノリティの権利保障」としました。「マイノリティ」、これは一部の方だけを指しているわけではなく、社会全体の話であり、自分たち自身の話です。子育てをすること、年を取ること、自分自身が様々な意味で弱い立場の当事者になることもありますし、固定的な「誰か」の話ではありません。「マイノリティが住みやすい社会こそが誰にとっても住みやすい社会である」そんな思いを区議会の場で伝えたいと思っています。
質問項目は、1. 性的マイノリティの権利保障について、2. 外国籍住民の権利保障および多文化共生社会の実現について、3. 待機児童対策について、4. まちづくりについて、そしてその他となります。(区のウェブサイトでも公開されています。)
宜しかったらぜひ傍聴にお越しください!
文教児童青少年委員会 練馬区の2016年4月の学童保育の待機児童について
昨日の委員会では、学童保育の待機児についての報告もありました。学童クラブの待機児については、あまり報道等で取り上げられてはいませんが、非常に深刻な状況です。
今年(2016年)の4月における学童クラブの待機児は289名で昨年よりも17名増加しています。その内訳をみると、1年生で57名、2年生で85名、3年生で145名です。
学童クラブの待機児童対策について確認すると、今後、ひろば事業、ランドセル来館、そしてねりっこクラブで対応するとのこと。
しかし、ひろば事業やランドセル来館は、あくまでもボランティアの方が中心となって子どもたちを「見守る」ものであり、学童クラブの求める保育とは全く異なります。また、ねりっこクラブについても、昨年度3校で開始されたばかりで、待機児童の増加には全く追いつかない状況です。そして、夏休みに緊急での対策として、待機児童の緊急受入を行うとのことですが、この対策も今年で4年目、もはや緊急ではなく、恒常的に必要な状況となっています。
そうした中、全体としては枠が300名分余っているのだから、そちらに通わせればいいのでは、という指摘があり、それにたいして練馬区も検討する、という話でしたが、学童クラブは、自分たちが通っている学校の近くで、友人たちと過ごすことが重要であり、遠くの施設が空いているから、そこに通わせればいい、という話では安全性の面から考えてもないと思います。
だからこそ、学童クラブの待機児童についても保育園と同様、質を維持しながら、学童クラブの増設を含めた根本的な解決を図るべきだと思います。
文教児童青少年委員会 練馬区の2016年4月の待機児童数について
昨夜の投稿でもご報告しましたが、昨日の委員会、今年(2016年)4月の練馬区の待機児童数が公表されました。練馬区では昨年、今年4月までに(新基準での)待機児童の数をゼロにすることを目標としていました。しかし、提出された数字を見ると、今年の待機児童は166人、昨年に比べて10
人しか減っておらず、むしろ旧基準での待機児童については、数十名増え399名となっています。
練馬区の説明では、想定していたよりも申込者が多かったため、とのことですが、この説明自体、毎年同じで、これまでも区の想定する児童数の計算根拠自体を改善すべきと訴えていました。
待機児童に対する区の対応を確認したところ、今後、保育所に空きが出た場合には紹介していく、ということだけで、区民の方からの陳情にもあった緊急対策を行う予定もないとのこと。また、この方々が現在どのように暮らしているか、聞き取りなどは行っていないとのことでした。
そもそも新基準での待機児童数の計算では、育休を延長できた方、また近くに認証等の保育所に空きがある方は待機児から除かれています。つまり、この166名については、ご家族が育休を延長できず、近くに認証等の保育所も空いていない、まさに待ったなしの状況の方々です。家庭外で保育が必要な方に対して保育を提供するのは区の義務であり、こういった方に対して練馬区からフォローをしないというのは、児童福祉の原則に反すると思います。
さらに、練馬区ではこの状況を受けて、来年4月を目標に「保育所待機児童ゼロ作戦」を実施し、待機児童の解消を目指すと発表(これは昨日のNHKでも取り上げられています)が、これまでは、来年の4月までには、より広い範囲の旧基準の待機児童(今年は399名)のゼロを目指すとしてのが、新基準(166名)のみをゼロとすると大きく目標を落としています。残念ながら少しも目新しい目標ではなく、むしろかなりの後退です。
だからこそ、練馬区として、現在の待機児童への緊急対策や、待機児の計算方法の見直しも含めた抜本的な対策をはかるべきだと思います。