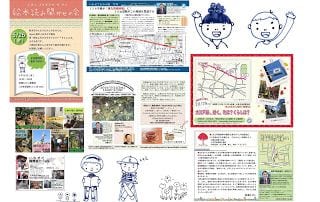日本最大のモスクへ!
先日、渋谷にある日本最大のモスク、東京ジャーミイの視察を行いました。
このモスク、創設は1917年のロシア革命に遡るとのこと。革命時、迫害を受けたトルコ系民族のタタール人(イスラム教徒)はシベリア、満州を経て、日本のこの地域にコミュニティを作ったとのこと。そして、1938年にこの地に初めてモスクを立てたそうです。そして、2000年に建て替えられたのが現在のモスクです。
私もパキスタンやヨルダンなどでいくつかのモスクを訪れていたのですが、日本のモスクは初めて。イスラム教もそれほど一般的ではないから、小さいのかな…などと考えながら一歩入ると、そこは別世界…あたかもイスラム教国に紛れ込んだような、完成度の高さに衝撃を受けました。
伺うと、この建物、コンクリートと水以外はすべてトルコから輸入したとのこと。床を覆うすべての大理石から、柱の一本一本まですべて海を渡ってきたそうです。そして、建築に携わった方々もトルコから来たそうで、100名以上が住み込みで働いたとのこと。
建物も、モスクは正面を中心に完全な線対称(シンメトリー)になっていて、正六角形の形になっているとのこと。また、天井の近くには、蜘蛛の巣を防止するために有効とトルコで思われているダチョウの卵が埋め込まれているそうです。
あまりの静けさ、荘厳さに圧倒されながら、ガイドの方の解説も伺いました。彼によると、日本ではイスラム教に対する偏見が強いが、それは「異文化」といういわば西洋的なフィルターを通じてイスラム教を見ているからとのこと。偏見を捨て、まっすぐ見なければ、異文化と向き合うことはできない、とのことでした。今の世界ではあまりに国家(nation state)の対立ばかりが取り上げられている、しかし、イスラムの教えにもあるとおり、国よりももっと根本的なつながり、に目を向けるべきだ、という指摘は印象的でした。冗談で言っていましたが、日本人はイスラム教徒といえば「豚肉を食べない、一夫多妻、テロリスト」といったようなイメージしかない、でも、本当に大切なのは、お互いの文化をしっかりと理解することである、とのこと。
練馬区でも登録済みの外国籍住民の方は1万7,000人を超え、区民の一人は外国人ということになります。そんな中で外国籍住民、特に在日の方を対象としたヘイトスピーチは近年急激に増加しています。こうした状況を改善して、真の多文化共生を実現するうえで一番基本となるのは、それぞれの文化を尊重し、理解することだと改めて実感しました。今後、地域で視察ツアーも企画したいと思いますのでぜひご参加ください^_^
市民の声ねりまの総会
日曜日、「市民の声ねりま」の総会が行われました。
「市民の声ねりま」の会員の皆さんとお会いして、1年の報告や今後についてお話する貴重な機会で毎年楽しみにしています。今回の総会、いつもお世話になっている方々、100名近くが参加してくださいました。
総会で、私の事務所からは、1年の振り返りとしてサポーターのチームができたこと、事務所を借りたこと、二名のスタッフが一緒に働いてくださっていること、そして、皆さんと市民講座(樋口陽一さん、和田春樹さん講演会など)やいわせてカフェなどを行っていることなどをご報告しました。
振り返ってみると、去年までは自宅を事務所として使っていて、サポーターのチームもありませんでした。それが、みなさんのご支援のお陰で、事務所も持てるようになり、継続して地域の中で活動できるようになったこと、改めてありがたいと実感しました。
久しぶりの懇親会
今日はサポーターの皆さんとの定例会。
一年の振り返りとともに、これから事務所で行うイベントについてお話しました。皆さんとお話して実感したのが、皆さんのおかげで事務所を持つことができて活動の幅がとても広がったな、ということ。「いわせてカフェ」や法律相談会のほか、定期的に絵本の読み聞かせをしたり、ご提案をいただきながら「大泉わくわく講座」という市民講座を2か月ごとに開催したり。そして、今月からは、ドキュメンタリーなどを一緒にみながら議論する会も開催することになりました。こうして皆さんの力を頂きながら、一つ一つの活動を積み重ねて、少しでも地域に根差していきたいと改めて思いました。
その後は久しぶりの一品持ち寄りの懇親会。天気も良かったので、お庭で行いました。自家製のサングリア(お酒は完全に飛ばしてありました。)、卵を使ったポテトサラダ、野菜たっぷりの煮物、古代米、唐揚げ、焼きコロッケ、豚の煮つけ、肉まん、ミルクレープなど、みなさんがそれぞれ準備してくださったもので、どれも材料から体にいいものばかり(因みに私は今回は時間がなく、ズルして生活クラブのロールキャベツ(味付けは私が行いました…))、久しぶりに皆さんとリラックスさせていただきました。
6月10日には、大泉わくわく講座の第三回目として、樹木のお医者さん(樹木医)の方をお招きして、講演会「樹木医から見た大泉のまちづくり」も行います。ぜひご参加ください!
軍艦、ハワイ、朝鮮…皆さんは「軍艦じゃんけん」、知っていますか?
先日、実家の母と久しぶりに話した際、近くの小学校に通う友人のお孫さんが、学校で友達から教えてもらったといって、じゃんけんの「ぐー、ちょき、ぱー」の代わりに「軍艦、ハワイ、朝鮮」と言い出したとのこと。驚くと同時に、私も小さいころ、意味を知らないままに、「軍艦、ハワイ、沈没」と言って遊んでいたことを思い出しました…調べたところ、「軍艦じゃんけん」と呼ばれていて、歴史ははっきりしてないものの、戦時中にできたと推定されるそうです。
皆さんのまわりでは軍艦じゃんけん、ありましたか?
このことから感じたのは、学校であまりに近現代史を教えてこなかったのではということです。知らないからこそ(私も含めて)、こうした遊びが無くならず、また、周囲が止めることもないのではないでしょうか。
私が外国籍住民との共生などについて駅等で訴えているとき、「南京大虐殺はなかった」とか、「従軍慰安婦はデマだ」とか、話しかけてくる方がいらっしゃるのですが、10代から20代の方が多く、「なぜそう思うのですか?」と聞くと、「インターネットや友人から学んだから。」とのこと。改めて聞くと、学校で近現代史はほとんど教えられなかったので、自身で勉強したとのことです。
ちょうど今、地域で日中韓の専門家が共同で編集した教科書「未来をひらく歴史」の読書会に参加していますが、それを読んでも日本の歴史教科書との違いも感じています。社会が、教育も含めてしっかりと歴史と向き合っていくこと、重要だと改めて感じました。
東京レインボープライド2017
GW最終日、代々木公園で行われた「東京レインボープライド2017」(TRP2017)に参加しました。議員を志した時、目標に掲げたことの一つが外国人や性的マイノリティなど、様々な価値観や多様性が尊重され、共存、共生する地域社会をつくることでした。だからこのフェスタ、毎年参加することを楽しみにしています。
会場につくと、去年よりも遥かに多いブース、そして参加者の方も性別や国籍を問わずおもいおもいのスタイルで楽しんでいる姿に、海外にいた頃を思い出しました。
海外にLGBTであることをオープンにしている友人は何人もいますが、そのアイデンティティを前面に出すことがタブー視されがちな日本では、カミングアウトしていない友人が大半です。「多様性の尊重」といいながらも、学校などでは性的マイノリティについて教えることはほとんどなく、私たちが議会で学校において性的マイノリティの子ども達への配慮を訴えても、なかなか前に進まないのが現状です。
だからこそ、こうしたフェスタなどを通じて、カミングアウトしやすい社会、またしなくても過ごしやすい社会に少しでも近づけばいいと改めて思うとともに、地域でしっかりと活動をしていかなければと改めて思いました。
憲法記念日におもうこと
憲法記念日の今日、地元の大泉9条の会の皆さんと共に、大泉学園駅で憲法の大切さについて訴えました。憲法ができて今年でちょうど70年、今ほど憲法が揺らいでいる時期はないと思います。
私が政治家を志した際、掲げた目標の一つが、「地域から平和と人権、憲法を守る」でした。(詳細はウェブサイトをご覧ください iwasetakeshi.net)。これは、私がこれまでパキスタンやコンゴ、ウガンダなど、紛争国で国際協力を行ってきた中で、紛争が子どもを含む人々の一生にどれほど残酷な事態をもたらすかを見たからです。
ウガンダでの活動時に仲良くなった同世代の運転手の方が、ある時「僕は子どもの時、兵士だったんだ。そして、もちろん銃も撃ったよ。」そんな話をしてくれました。私が驚いて「人を撃ったこともあるの?」と聞くと「当然だろ、銃の先に何があると思っているんだ?」と怪訝そうに聞かれたのが衝撃的でした。
当時の私にとって、銃を撃つということは映画やゲームなど、遠い世界の出来事だと感じていたのですが、それがあまりに日常にあるということに気づかされました。
同時に彼が「テレビで見たのだけど、日本には軍隊がないんだろ、本当に羨ましいよ。戦争なんてどんな理由があっても絶対ダメだ。政府がどんなに美しいことを言ったって、人殺しに正義なんてない。そして、武器がある限り戦争はなくならないんだよ」と話していたのが印象的でした。
朝鮮半島やシリアなど国際情勢が緊迫している中、日本でも戦争に備えるべき、といった議論も行われています。でも、こんな状況だからこそ、日本こそが平和の大切さを訴えていくべきだと思いますし、そのためにも憲法は絶対に守らなければならない、と改めて思いました。
今年に入って、地域で憲法について考えるために、ゼミの恩師でもある憲法学者の樋口陽一先生、歴史学者で「大泉市民の集い」の発起人でもある和田春樹さんをお招きして講演会や勉強会などを企画してきました。
その中で、樋口先生は立憲主義について、「立憲主義は闇夜を照らす灯台のようなものだ。晴れているときはなくてもいいと思うが、それが行き詰った時にこそ、ましてや防風が吹きすさぶ時こそ灯台(立憲主義)の重要性が問われる」と言っていましたが、安保関連法制が成立し、共謀罪までもが可決されようとしている、まさに今が防風の中にあり、今こそ立憲主義の重要性が問われていると思います。
私たちも地域の中で、これからも憲法の大切さを訴えていきたいと思います。
多言語でのウェブサイト、できました!
議員を志すうえで、最も実現したかった事の一つ、それが、地域で国籍や民族などの異なる人々が互いの違いを尊重し、地域社会の一員としてともに生きる、多文化共生社会を実現することでした。
その小さな一歩として、私のウェブサイトで、英語、スペイン語、韓国語での説明も掲載をはじめました。区のウェブサイトなどでは機械による自動翻訳が多いのですが、内容が間違っている、また、意味をなさないことも頻繁にあるので、私たちはすべてボランティアの方々との共同作業で行いました。おかげで時間はかかりましたが、ようやく完成することができました。
外国籍の方からも多くご相談を頂き、伊藤朝日太郎弁護士と一緒に行っている無料の法律、生活相談でも多くの外国籍の方がお越しになっている中で、今後も様々な形で多言語での情報を発信していきたいと思います。ぜひご覧ください!
南米エクアドルで車いすの大統領が誕生します、日本では?
私が議員になるまで2年にわたって活動していた南米のエクアドルで5月から車いすの大統領、レニン・モレノ氏(Lenín Moreno)が誕生することになりました。南米も含めて、世界が右傾化している中で、エクアドルでは左派政権が続くことになります。
このモレノ氏、1998年に車で強盗にあい、銃撃を受けて、両足の自由を失ったとのこと。その後、うつ状態に苦しんだものの、「犯人を許す」という心境に達し、心が解放されたそうです。その後、ユーモアや愛、友人や家族との繋がりこそが痛みを癒す、という考えで多くの著書も記しています。
今回の大統領選挙では、右派の候補である銀行家を接戦で破り、「私はすべての国民のための、中でも特に貧しい人々のための大統領になる。」と言っています。(毎日新聞の記事より)
一方で、日本を見ると、障害者差別禁止法などは成立したものの、障がいを持つ政治家はまだまだ一握りです。日本は経済大国として、エクアドルに対しても毎年、多くの技術支援を行っていますが、むしろ日本がエクアドルや、ムヒカ元大統領の国、ウルグアイなどから学ぶべきことも多いと思います。
http://www.asahi.com/articles/DA3S12880466.html
(写真は2014年、集落でのワークショップの様子です。)
週末の活動 ダグラス・ラミスさんの講演会といわせてカフェ
週末は3つのイベントに参加しました。最初は私も会員になっているNPOのふらじゃいるの総会。こちらの団体、地域で精神障がいを持つ方、そしてサポートする方々など、当事者による団体で、当時者同士で支えあうことが効果的である、という考えに基づいて「当事者研究」などを毎週行っています。総会も皆さんの普段の活動が伝わる暖かい雰囲気で行われて、その後の懇親会で皆さんとゆっくりとお話もできて、私も元気を頂けました。
その後、「世界が百人の村だったら」などの著者で政治学者のダグラス・ラミスさんの講演会に参加しました。ラミスさん、実はPARC自由学校で私の妻や義母の英語の先生だったこともあり、当時から大変お世話になっていました。特に、妻にとっては、最初に国連で働くという夢について背中を押してくれた方でもあったので、私も楽しみにしていました。
ラミスさんの憲法改正や、沖縄に関するお話。クリティカル(批判的)だけどユーモアに富んでいて、小学生でわかるような言葉で話すのが印象的でした。特に、沖縄に米軍基地の75%が集中している状況について、「日本が100人の村だったとしたら、沖縄が1人でそれ以外が99人、みんなでレストランで支払いをする際に、沖縄の人の意見を聞かずに、沖縄だけが75,000円支払って、残りの人は250円程度ずつしか支払わない、と決めてしまうのと同じことだ。」という例えが非常にわかりやすかったです。そして、私たちがすべきこととして、まずは沖縄の負担を正確に理解することが必要である、という指摘、その通りだと思いました。
そして、日曜日は「いわせてカフェ」を西大泉で実施。こちらのカフェ、少人数の皆さんとお茶を飲みながら、ゆっくりと政治のことや地域のことなど、自由にお話しようというもの。西大泉で行うのは1年振りで、宣伝の機会も限られていたので、誰も来なかったらどうしようと心配だったのですが、実際には支援者の方を含めて、合計で8名の方が参加してくださり、それぞれのお仕事などについてお話いただきました。今回は、障がい者支援に関わる方が多く、現在の福祉政策の課題などについて、それぞれのご経験からお話を伺うことができ、私にとっても勉強になりました。
その後、家に帰って息子と近くの公園をお散歩。皆さんから力をいただける素晴らしい週末でした、また一週間頑張ります!